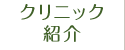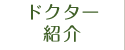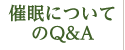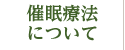» 催眠についてのQ&A
以下に、催眠についてよくある疑問についてのお答えをまとめてみました。
- 催眠は催眠療法家のパワーにより治療効果を発揮するのですか?
- そうではありません。催眠療法は、患者様と治療者の信頼関係をベースに、患者様にとって安全な場として機能する催眠状態を利用して行われます。患者様と治療者の関係は協働的なもので、治療者は患者様の持ち合わせている能力、いわゆるリソースを患者様の力でうまく使えるようにお手伝いするスタンスです。野球のピッチャーとキャッチャーにたとえれば、患者様がピッチャーで治療者はむしろキャッチャーの役割を果たします。したがって、万能の力をもった治療者が一方的に患者様に暗示などを植え付けるものでは決してありません。
- 催眠状態に入ると自身のコントロールを失うのですか?
- 催眠状態に入っても、自身をコントロールする力はもち続けることが出来ます。テレビなどを通じて催眠を知っている方は、催眠状態に入ると鶏のように鳴かされてしまったり、言いたくないことまで言わされてしまう、との誤解をもっておられるかもしれません。しかし催眠状態に入っても自身のコントロールを失うことはないので、仮に治療者にしたくないことを言われたとしてもしないで済ますことができます。また言いたくないことは治療者に隠すこともでき、治療者に嘘をつくこともできます。テレビなどに見られるいわゆるショー催眠はおそらく「やらせ」ではないものの、催眠者(催眠を施す人)の暗示にうまく反応する人を事前にさりげなく選択しており、被催眠者(催眠を施される人)は催眠者がどのような反応をすれば喜ぶかを無意識に知っており、無意識に協力していると考えられます。
- 催眠には誰でも入るのですか?
- 全ての人が催眠状態に入るわけではありませんが、大多数の方は催眠に入ることができます。実験的には、非常によく催眠に入る人、中くらい程度に催眠に入る人、少し催眠に入る人、そしてほとんど催眠に入らない人、がそれぞれ4分の1ずつくらいいるとのデータがあります。ただ、催眠に入るかどうかは患者様の体質的なものだけで決まっているのではなく、患者様と治療者との信頼関係で大きく変わってきます。もともと催眠に入りにくい方でも、「この治療者なら信頼できる」との安心感があれば非常に催眠に入りやすくなります。逆に「この治療者の催眠には入りたくない」と患者様が思われるようなら、催眠には入りません。患者様に信頼される関係を築くことは治療者の仕事ですので、患者様が「治療者に協力しなければ」と必死に努力していただく必要はありません。
- 催眠状態に入るのは意志の弱い人、あるいは知能が低い人なのですか?
- そうではありません。催眠状態は多くの場合、「注意が集中された状態」と説明されます。そのため、集中力の高い人は催眠に入りやすく。集中できにくい人は催眠に入りにくいと言えます。したがって、意志の強さや知能の高さとは平行しません。
- 催眠の深さについて教えて下さい。
- 催眠にはおおよそ、浅い催眠、中くらいの深さの催眠、深い催眠があります。催眠から覚醒した後の自覚的な体験としては、浅い催眠では「言われたことは全て覚えてますが、私は本当に催眠に入ってましたか?」という感想になることが多くなります。一方、深い催眠から覚めた後には「私、眠ってましたか?」と訊かれることが多く、治療者の言うことはほとんど覚えていなかったりします。中くらいの催眠ではそれらの中間で、治療者の言葉を覚えていたり、覚えていなかったり、ということになります。治療者の言葉(暗示)を覚えていないと感じている場合でも、暗示は直接に患者様の無意識に届いていると考えられ、忘れてしまっているわけではありません。そのため、自覚的には覚えていなくても治療効果を期待できます。むしろ意識に上らないためにそれまで無効であった意識的な努力が回避されるため、治療効果が上がりやすいこともあります。また自覚的には催眠に入る時には眠気をともなうことも多いですが、「言われたことを覚えていられるようにちゃんと起きていなくちゃ」と思われる必要はなく、眠ければ眠っているかの状態に自然に入っていただいてかまいません。
催眠の深さと治療効果は必ずしも平行せず、心理療法的な催眠ではむしろ中くらいの催眠で一番変化が起こりやすいとも言われます。疼痛のような身体的な問題が焦点である時には、深い催眠の方が有効である場合もあります。催眠の深さも患者様の生得的な体質だけで決まっているわけではなく、患者様と治療者との信頼関係が築けていることが治療に大きな力を発揮します。 - 深い催眠に入れば全ての催眠現象が体験できるのですか?
- 催眠状態に入ると、普段の意識状態よりも顕著に体験しやすくなる現象があり、それらは「催眠現象」とよばれています。過去のことを現在のことのように体験し直す「年齢退行」なども、催眠現象の1つです。しかし催眠体験は個々人によって非常に異なるもので、人によって体験しやすい体験と体験しにくい体験があり、全ての人が全ての催眠現象を体験できるわけではありません。それでも多くの場合、治療に必要な催眠現象を治療者がうまく利用して治療効果を上げることができます。
- 催眠状態に入るためには必ず催眠誘導が必要なのですか?
- 必ずしも催眠誘導を行わなくても催眠状態には入れます。繰り返しになりますが、催眠状態は「注意が集中された状態」と説明されます。それは普段、全ての人がそうと知らずに入っている状態です。たとえば、面白いテレビに熱中していて「ご飯ができた」と呼ばれても気づきにくい状態、街角を歩いていて偶然長年好きな音楽に心を奪われる状態、などがそうです。あるいは、スポーツをやっていて自分でも驚くほど身体が勝手に動いてくれるような状態、祭りにおけるようなある種の陶酔状態なども、自然発生的な催眠状態と考えられています。厳密には、こうした自然発生的な意識の変性状態を「トランス」、催眠誘導という意図的な作業を通して入る意識変性状態を「催眠状態」と呼んで区別されますが、治療上は同じように利用されています。したがって、患者様が自分なりに自然なトランスへの入り方がうまいようなら、その方法でトランスに入ってもらうのがよい催眠療法の入り口と考えられます。
- 催眠に入っても必ず目が覚めるのですか?
- 催眠からは必ず覚醒します。「催眠からうまく覚めない」という場合のほとんどの原因は、覚醒のための暗示が不十分なことにあります。つまり、しっかりと覚醒暗示を与えられていれば問題なく覚醒します。ただし、「解離性障害」という特殊な病態では自然にトランスに入ってしまいやすい病的な性質があるため、こうした患者様に対して催眠療法を行う場合には特に覚醒のための暗示をしっかり行うように治療者が心がける必要があります。
- その他の催眠療法による有害事象について教えて下さい。
- 催眠はよく外科医のメスにたとえられます。外科医のメスと一緒で、その使い方により人を助けるためにも使われうるし、人を傷つける可能性もないわけではない、ということです。つまり、メスが良いか悪いかではなく外科医の良し悪しが問題であるように、催眠療法を行う際に問題になるのは催眠自体ではなく、治療者による催眠の利用の仕方です。催眠療法が治療のために十分な効果を発揮できないことは時々にあるものの、治療者が患者様に対して無理を強いることがなければ有害事象は生じない、と考えてよいと思われます。治療者が無理をする場合の例としては、心的外傷後ストレス障害の患者様がまだ外傷体験に対して向き合う心の準備ができていないにもかかわらず、治療者が急いでそれを強いてしまう場合、などがあります。
- 催眠を使えば瞬時によくなるのですか?
- 多くの場合は、1、2回の催眠セッションで治療が終わりになることはありません。お困りの問題にもよりますが、催眠の適応がある病態なら、催眠を利用しないよりも速やかな治療効果が期待できます。一方で、催眠を利用すれば長年悩んでこられた問題が瞬時になくなるというのは誤解と言わざるをえません。患者様が長い年月の間抱えてこられた問題を短時間で消し去ったり解決したりするのは、どのような治療によっても難しいでしょう。ただ、もし催眠がご自身に合っているとすれば、何回か催眠のセッションを体験していただく中で少しずつ回復している感覚をもてるようになると期待できます。
- 何回くらい催眠をやれば治療が終わるのですか?
- 患者様の抱えておられる問題は個々人により異なるため、実際には治療者にも何回くらい催眠を行えば十分であるのか予想が立たないことが少なくありません。ただ、非常に大雑把には精神科的な診断によりおおよその治療期間を予想することが出来ます。現実的には、患者様が理屈でなく「催眠はもう終わりにできる」と感じられる時期が催眠をいったん終了にするに適切なタイミングであることが多いように思われます。
- どれくらいの頻度で催眠を行えば良いのですか?
- 多くの場合は、2週間に1度で大丈夫と考えています。逆に1ヶ月以上間隔があいてしまうと、毎回の治療による効果の積み上げが難しくなります。病態によって、たとえば気分の変動が激しかったり、衝動性が見られる患者様などには毎週のご来院をお勧めする場合もあります。